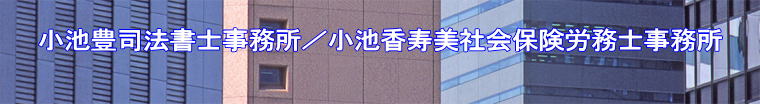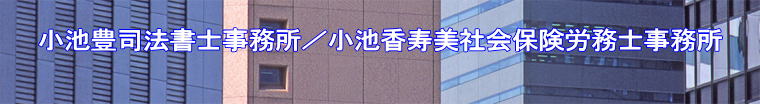| 住宅用家屋の所有権保存登記の税率 1000分の1.5 |
| 租税特別措置法第73条 → 令和9年3月31日まで |
| 住宅用家屋の所有権移転登記の税率 1000分の3 |
| 租税特別措置法第74条 → 令和9年3月31日まで |
特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記の税率 1000分の1
特定認定長期優良住宅の所有権の移転登記の税率 1000分の1
(但し、一戸建ての特定認定長期優良住宅の所有権の移転は、1000分の2) |
| 租税特別措置法第74条の2 → 令和9年3月31日まで |
認定低炭素住宅の所有権の保存登記の税率 1000分の1
認定低炭素住宅の所有権の移転登記の税率 1000分の1 |
| 租税特別措置法第74条の3 → 令和9年3月31日まで |
| 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率 1000分の1 |
| 租税特別措置法第75条 → 令和9年3月31日まで |
| 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権設定登記の税率 1000分の1 |